昇格試験で「インバスケット試験」があると聞いたものの、どのような試験なのか分からず不安に感じていませんか?
「どんな問題が出るの?」「どうやって対策すればいいの?」と悩んでいる方も多いでしょう。
インバスケット試験は、限られた時間内に業務上の課題を処理し、管理職としての適性を評価する試験です。
一般的な筆記試験とは異なり、正解が1つではなく、判断力や優先順位のつけ方が問われるため、適切な対策が不可欠です。
本記事では、インバスケット試験の特徴、出題される問題のパターン、解答のコツ、具体的な対策方法まで詳しく解説します。
この記事を読むことで、試験の内容を理解し、適切な準備を進めることができるようになります。
「インバスケット試験に不安を感じている方」「試験で高得点を目指したい方」は、ぜひ最後まで読んで、実践的な対策を身につけてください!
インバスケットとは?基本の概要
インバスケットとは何か、どのような場面で活用されるのか、その歴史や背景について詳しく解説します。
インバスケットとは何か
インバスケット(In-Basket)とは、与えられた業務上の課題に対して、限られた時間内で適切な対応を判断するシミュレーション形式の試験やトレーニング手法です。
「In-Basket(インバスケット)」とは英語で「未処理箱」や「未決箱」を意味します。もともとアメリカ空軍で開発され、管理職候補者の適性を判断するために使われてきました。
試験では、管理職やリーダーの役割を担う受験者が、机の上に積まれた未処理の案件を迅速かつ的確に処理しなければなりません。問題には「正解」が存在せず、受験者の思考力や優先順位の付け方が評価されるのが特徴です。
インバスケットが用いられる場面
インバスケットは、企業や公的機関の人材評価や研修で活用されています。具体的には以下のような場面で用いられます。
- 昇格試験:管理職候補者の適性を測るため
- 採用試験:リーダー職やマネジメント職の選考プロセスの一環
- 研修・トレーニング:実務に即した判断力や業務処理能力を鍛えるため
具体的な試験事例
たとえば、企業の昇格試験では以下のようなケースが想定されます。
試験シナリオ例:
あなたは営業部の課長として、新規案件の受注を進めながら部下の育成にも携わっています。朝出社すると、机の上には次のような未処理案件が積まれています。どのように対応しますか?
- 取引先からのクレーム(緊急度:高)
- 上司からの会議資料作成の指示(期限:本日午後)
- 部下が遅刻しており、連絡が取れない(対応:未定)
- 顧客からの新規案件の問い合わせ(成約の可能性あり)
あなたはこれらの案件に対し、限られた時間の中で優先順位を付け、適切な対応を考えなければなりません。
インバスケットの歴史と背景
インバスケットは1950年代にアメリカ空軍で開発されました。当時、軍の幹部候補生の指導力や意思決定能力を評価する目的で導入されました。
その後、企業の人材育成や評価制度に応用され、1990年代以降、日本でも広く普及するようになりました。現在では、多くの企業や公的機関の昇進試験・リーダーシップ研修・マネジメントスキル向上プログラムとして採用されています。
インバスケットの特徴とは?
インバスケット試験には、一般的な筆記試験とは異なるいくつかの特徴があります。
特に、実務に近い形で能力を評価できることが大きなポイントです。
ここでは、インバスケットの基本的な特徴や評価のポイント、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
インバスケットの基本的な特徴
インバスケット試験の特徴を理解することで、どのような能力が求められるのかを明確にできます。
主な特徴は以下のとおりです。
- 実務に即した試験である
- 短時間で判断を下す能力が求められる
- 「正解がない」試験である
特徴1:実務に即した試験である
- インバスケット試験は、架空の業務シナリオのもとで行われます。
- 受験者は管理職やリーダーの立場になりきり、限られた時間内で適切な意思決定を行う必要があります。
- 「単なる知識の暗記」ではなく、実際の業務をどのように進めるかを判断する力が問われます。
たとえば、「営業部の課長」「総務部のマネージャー」「工場長」といった役職の設定があり、それに応じた業務案件が出題されます。
特徴2:短時間で判断を下す能力が求められる
- インバスケット試験では、時間制限の中で複数の案件を処理する必要があるため、迅速な意思決定が求められます。
- すべての案件に完璧に対応することは難しいため、優先順位を明確にし、最も効果的な対応を選ぶ力が重要になります。
試験の制限時間は1~2時間程度で、10~20件の案件を処理しなければならないことが一般的です。
そのため、時間管理能力も試されます。
特徴3:「正解がない」試験である
- インバスケット試験には、「唯一の正解」が存在しません。
- 受験者の判断基準や意思決定のプロセスが評価されるため、論理的な説明が求められます。
- 同じ問題に対しても、受験者によって異なる答えが出ることがありますが、重要なのは「なぜその決断をしたのか」を明確に説明できることです。
このような特徴があるため、対策が難しい試験とも言えます。
しかし、評価基準を理解し、適切な判断基準を持つことで、試験に対応できるようになります。
インバスケットの評価ポイント
インバスケット試験では、主に以下の4つの観点で評価されます。
- 優先順位の設定
- 意思決定のスピードと正確性
- コミュニケーション力
- 問題解決能力
1. 優先順位の設定
- 限られた時間内に、どの案件から対応するかを決める能力が求められます。
- 重要度(Importance)と緊急度(Urgency)のバランスを考え、適切な順番で処理することが重要です。
たとえば、「クレーム対応」と「上司からの資料作成指示」があった場合、クレーム対応を優先するのが一般的です。
なぜなら、クレームを放置すると顧客の信用を失い、企業全体の利益に悪影響を与える可能性があるためです。
重要度と緊急度については以下の記事を参考にどうぞ。

2. 意思決定のスピードと正確性
- 迅速に判断し、適切な対応を取れるかが評価されます。
- 迷って時間を使いすぎるより、一定の基準で素早く決断することが大切です。
たとえば、「部下から相談を受けたが、自分の業務も忙しい」という状況では、すぐに対応できるか、他の人に任せるかを判断する必要があります。
3. コミュニケーション力
- 部下、上司、取引先など、さまざまな関係者との適切なコミュニケーションが求められます。
- 報告・連絡・相談(ホウレンソウ)がしっかりできるかどうかも重要な評価基準になります。
たとえば、部下がトラブルを起こした場合、事実確認をしたうえで上司に報告し、適切な対応策を提示することが求められます。
4. 問題解決能力
- 発生した問題に対して、最適な解決策を見つけられるかが評価されます。
- 過去の経験や知識を活かし、リスクを最小限に抑えながら対応することが重要です。
たとえば、「取引先が納期遅延に怒っている」という状況では、謝罪だけでなく、代替案を提示することで信頼を回復できる可能性があります。
上記以外で評価項目される能力は以下をご覧ください。

インバスケットのメリットとデメリット
インバスケット試験には、他の試験と比較して以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 実務に近い形で能力を評価できる
→ 実際の業務を想定した試験のため、管理職としての適性が明確に分かる。 - 知識ではなく、実践的なスキルが問われる
→ 記憶型の筆記試験とは異なり、実際の業務で必要な判断力や優先順位付け能力を評価できる。 - リーダーシップやマネジメント能力を測定しやすい
→ 部下への指示の出し方、上司や取引先との関係構築力が重要視されるため、管理職としての適性を見極めやすい。
デメリット
- 試験対策がしづらい
→ 一般的な知識試験と違い、暗記や学習ではカバーできないため、経験者が有利になりやすい。 - 主観的な評価が入りやすい
→ 「この答えが正しい」と明確に決められないため、試験官の評価基準によって結果が変わることがある。 - 正解が一つではなく、判断基準が曖昧になりがち
→ 受験者によって答えが異なるため、どの対応が最も適切だったのかを客観的に評価するのが難しい。
インバスケットの問題形式と例題
インバスケット試験では、実際の業務を模した問題が出題され、受験者は管理職やリーダーとして適切な対応を求められます。
この章では、インバスケットの問題形式やよくある出題パターン、具体的な例題とその解説について詳しく説明します。
典型的なインバスケット問題の構成
インバスケット試験の問題は、一般的に以下のような構成になっています。
- 問題文(シナリオ)
- 試験の設定や業務環境が説明される。
- 例:「あなたは営業部の課長です。今朝出社すると、以下のような案件がデスクに届いていました。」
- 状況説明(未処理案件のリスト)
- 実際に処理すべき課題が提示される。
- 例:「取引先Aからのクレーム対応」「部下Bの遅刻」「上司からの会議資料作成依頼」など。
- 選択肢または自由記述
- 選択肢がある場合:「Aを優先する」「Bを優先する」など複数の対応策から選ぶ。
- 自由記述の場合:「どのように対応するかを200字以内で記述しなさい。」
ポイント:
- 問題の内容は実際の業務と類似しているため、現実的な判断力が求められる。
- 「正解が1つではない」ため、受験者の思考プロセスが評価される。
よく出る問題のパターン
インバスケット試験では、以下のような問題がよく出題されます。
1. 優先順位の判断
【問題例】
あなたのデスクには、以下の4つの業務案件が積まれています。どの順番で対応しますか?
- 取引先からの緊急クレーム(このまま放置すると契約解除の可能性がある)
- 上司からの会議資料作成の依頼(期限は当日午後)
- 部下が体調不良を訴え、早退を希望している
- 新規案件の提案依頼が届いている(締切は3日後)
【解答例】
優先順位を決定する際には、「緊急度(Urgency)」と「重要度(Importance)」を基準に考えます。
| 案件 | 緊急度 | 重要度 | 優先順位 |
|---|---|---|---|
| 取引先のクレーム | 高 | 高 | 1位 |
| 部下の体調不良 | 高 | 中 | 2位 |
| 上司の資料作成 | 中 | 高 | 3位 |
| 新規案件の提案 | 低 | 高 | 4位 |
したがって、
- まず取引先のクレーム対応を最優先。
- その後、部下の体調確認をし、早退の手続きを行う。
- 資料作成は午後までに完成させる。
- 新規案件は締切に余裕があるため、明日以降に対応する。
緊急度と重要度の考え方については以下の記事を参考にどうぞ。

2. 部下のマネジメント(指導・育成)
【問題例】
部下のCさんが最近、業務のミスが多くなっています。先週は重要な顧客とのミーティングの日程を間違えてしまい、取引先からクレームが入りました。今日も別の案件でミスをしており、あなたのもとに謝罪に来ました。あなたはCさんにどのような指導を行いますか?
【解答例】
部下の指導では、頭ごなしに叱責するのではなく、改善策を一緒に考えることが重要です。
- まず、事実確認を行う。
- Cさんに「なぜミスが起きたのか」を考えさせる。
- 具体的な改善策を提示し、実行できるようサポートする。
回答例(200字):
Cさんの業務ミスについて、まず原因を確認し、なぜ間違えたのかを考えさせます。
そのうえで、「スケジュール管理を徹底するために、共有カレンダーを活用する」「業務の優先順位を整理するために、タスク管理シートを導入する」などの具体策を提案し、実行状況を定期的にチェックします。
3. クレーム対応(リスク管理)
【問題例】
取引先D社から「納期遅れが発生し、大きな損害を受けた」とクレームが入りました。D社は契約解除を検討していると伝えてきました。あなたはどのように対応しますか?
【解答例】
クレーム対応では、「即対応する」「誠実な姿勢で謝罪する」「具体的な解決策を提示する」の3点が重要です。
- すぐに取引先D社へ連絡し、状況を確認する。
- 遅延の理由を説明し、誠意をもって謝罪する。
- 遅れを挽回するための代替策(納期短縮の方法、補償の提案など)を提示する。
回答例(200字):
まずD社に速やかに連絡し、納期遅延の経緯を説明します。次に、誠意をもって謝罪し、取引先の信頼回復に努めます。具体的な対策として、「別ルートでの配送を手配し、納期を1日短縮する」「価格の一部割引を提案する」などの選択肢を提示し、相手の納得を得られるよう努めます。
4. 業務の効率化とタスク管理
【問題例】
あなたのチームは、複数のプロジェクトを同時進行しています。しかし、進行が遅れており、納期に間に合わない可能性が出てきました。
さらに、メンバーから「業務負担が重すぎる」という不満の声も上がっています。あなたはチームのリーダーとして、どのように対応しますか?
【解答例】
業務の効率化やタスク管理に関する問題では、「リソースの最適配分」と「チームのモチベーション向上」の2つを意識することが重要です。
- プロジェクトごとの進捗状況を確認し、優先順位を整理する。
- 業務を適切に分担し、リソースの配分を最適化する。
- メンバーの不満をヒアリングし、必要に応じてサポートを提供する。
回答例(200字):
まず、各プロジェクトの進捗状況を確認し、優先度の低い業務を後回しにすることでリソースを確保します。
次に、メンバーの負担が偏っていないかを確認し、業務を適切に分担します。
必要であれば、外部リソースの活用やスケジュール調整を検討し、無理のない形で納期を守るよう調整します。
5. 部署間の対立・調整対応
【問題例】
あなたの会社では、営業部と製造部の間で意見の対立が発生しています。
営業部は「より多くの製品を早く作るべき」と主張し、製造部は「品質を優先するため、急ぎすぎるとミスが増える」と反論しています。
両者の意見が対立し、業務の進行に影響が出始めています。あなたはどのように対応しますか?
【解答例】
部署間の対立を解決する際には、「双方の立場を理解し、共通のゴールを見つけること」が重要です。
- まず、営業部と製造部の両方の意見をヒアリングする。
- 共通の目標(例:売上向上や品質維持)を明確にする。
- 解決策を提示し、双方が納得できる形で調整する。
回答例(200字):
まず、営業部と製造部の双方から意見を聞き、問題の本質を理解します。
次に、「品質を維持しながら、可能な範囲で生産スピードを向上させる」という共通の目標を設定します。
具体策として、「生産ラインの効率化」「営業と製造の定期的な打ち合わせ」などを提案し、双方の納得を得る形で調整を図ります。
6. 突発的なトラブル対応(緊急事態の処理)
【問題例】
朝、出社すると、システムトラブルが発生し、社内の業務がストップしています。
IT部門は復旧作業を進めていますが、復旧までに数時間かかる見込みです。
一方、取引先との重要なオンライン会議が1時間後に予定されており、通常のシステムが使えない状態です。
あなたは管理職として、どのように対応しますか?
【解答例】
緊急事態においては、「状況の把握」「関係者への報告」「代替策の検討」の3つが重要です。
- まず、トラブルの影響範囲を確認し、緊急度を判断する。
- 取引先へ早急に連絡し、事情を説明する。
- 代替手段(別のシステム、電話会議の活用など)を検討し、迅速に対応する。
回答例(200字):
まず、IT部門から復旧の見込みを確認し、対応策を検討します。
取引先にはすぐに連絡を入れ、状況を説明し、オンライン会議の時間変更や代替手段(電話会議、別のシステムの利用)を提案します。
社内向けには、影響を受ける部署へ速やかに周知し、業務の遅れを最小限に抑えるための指示を出します。
7. 部下のモチベーション管理とチームビルディング
【問題例】
あなたのチームの若手社員Dさんは、最近仕事に対するモチベーションが低下しています。
上司からの評価は悪くないものの、Dさん自身が「自分の仕事に手応えがない」「このままでいいのか不安だ」と感じています。
あなたはDさんの上司として、どのように対応しますか?
【解答例】
部下のモチベーション管理では、「原因の特定」「適切なフィードバック」「成長の機会を提供する」の3つがポイントです。
- Dさんの悩みをヒアリングし、不安の原因を明確にする。
- これまでの成果を振り返り、ポジティブなフィードバックを行う。
- 新しい業務への挑戦機会を提供し、成長意欲を高める。
回答例(200字):
まずDさんと1対1で話し合い、不安の具体的な要因を探ります。
これまでの仕事ぶりを評価し、彼の強みや成長した点を伝えます。
さらに、スキルアップの機会として、新しい業務や研修への参加を提案し、やりがいを感じられる環境を整えます。
8. 上司との関係構築(報連相の強化)
【問題例】
あなたの上司は非常に忙しく、なかなかコミュニケーションを取る時間がありません。
しかし、あなたの業務には上司の判断が必要な案件が多く、進捗が滞ることがあります。
この状況を改善するために、あなたはどのように行動しますか?
【解答例】
上司との関係構築では、「報連相の工夫」「効果的なコミュニケーション手段の活用」「判断を仰ぐタイミングの最適化」が重要です。
- 報告のタイミングを工夫し、簡潔かつ要点をまとめて伝える。
- 定期的な打ち合わせを提案し、業務の優先順位を共有する。
- メールやチャットを活用し、上司の負担を軽減する形で報連相を強化する。
回答例(200字):
上司が忙しいことを考慮し、重要な案件の報告を優先するために、事前に議題を整理しておきます。
週に1回、短時間でも進捗報告の時間を確保できるよう提案し、上司と共通認識を持てるようにします。
また、簡潔なメールやチャットを活用し、判断を仰ぎやすい環境を整えます。
9. コンプライアンス違反の可能性がある事例の対応
【問題例】
部下Eさんが取引先との交渉を担当していますが、最近、取引先から「特別な便宜を図ってほしい」との要望を受けたとのことです。
直接の金銭授受はないものの、便宜を図ることが業務上のルール違反になる可能性があります。
Eさんは「取引先との関係を悪化させたくない」と悩んでいます。あなたは上司としてどのように対応しますか?
【解答例】
コンプライアンス問題に対処する際には、「事実確認」「適切な判断」「再発防止策」の3つが重要です。
- Eさんから具体的な状況を聞き、事実を整理する。
- コンプライアンス違反の可能性がある場合は、上司や法務部門と相談し、適切な対応を決める。
- 部下に対して、今後の対応方針を明確にし、再発防止策を講じる。
回答例(200字):
まず、Eさんから具体的な状況を詳しく聞き取り、どの程度のリスクがあるのかを判断します。
その上で、法務部門と相談し、適切な対応策を決定します。
取引先には、「社内規則に従って対応できない」ことを丁寧に説明し、関係を維持しながらもルールを守るよう指導します。
10. 社内トラブルとクレーム対応(ハラスメント問題)
【問題例】
あなたの部署のベテラン社員Fさん(勤続20年)が、新入社員Gさんに対して厳しい指導を行っています。
Gさんは「Fさんの指導が厳しすぎて、精神的に辛い」と相談してきました。
一方で、Fさんは「新人には厳しく指導しなければ育たない」と主張しています。
あなたはこの問題にどのように対応しますか?
【解答例】
ハラスメント問題に関しては、「事実確認」「関係者の調整」「再発防止策の実施」の3つが重要です。
- FさんとGさんの双方から状況をヒアリングし、事実を把握する。
- Fさんに対し、指導方法を見直すよう促し、Gさんにはメンタル面のサポートを行う。
- 職場全体の教育体制を見直し、適切な指導方法を共有する。
回答例(200字):
まず、FさんとGさんの両者から話を聞き、事実関係を明確にします。
その上で、Fさんには「厳しすぎる指導が部下の成長を妨げる可能性がある」ことを伝え、適切な指導法を検討するよう促します。
一方で、Gさんにはメンタルサポートを行い、必要に応じて上層部や人事部と連携してフォローを行います。
また、今後同様の問題が発生しないよう、指導方法に関する研修を実施し、部署全体の教育方針を見直します。
インバスケット試験では、以下のようなシチュエーションでの判断力が試されます。
- 優先順位の判断(業務の緊急度と重要度のバランス)
- 部下のマネジメント(指導・育成)
- クレーム対応(リスク管理)
- 業務の効率化とタスク管理(チームの負担軽減)
- 部署間の対立・調整対応(関係者間の意見調整)
- 突発的なトラブル対応(緊急事態の処理)
- 部下のモチベーション管理とチームビルディング(働きやすい環境づくり)
- 上司との関係構築(報連相の強化)
- コンプライアンス違反の可能性がある事例の対応(法令遵守とリスク管理)
- 社内トラブルとクレーム対応(ハラスメント問題)(職場環境の適正管理)
効果的な試験対策としては、以下のポイントを意識しましょう。
- 日頃から業務の優先順位を意識しながら仕事をする。
- 過去問や模擬試験を解き、試験形式に慣れる。
- ロールプレイングを活用し、実践的な判断力を磨く。
- 論理的な説明ができるよう、普段から思考プロセスを整理する習慣をつける。
実際の問題を解いてみたい方は以下の記事を参考にどうぞ。


インバスケットの回答例と回答のコツ
インバスケット試験では、単に「正しい答え」を出すのではなく、論理的な判断プロセスを示し、管理職やリーダーとして適切な対応ができるかどうかが評価されます。
この章では、効果的な回答のポイント、具体的な回答例、解答を作成する際の注意点について詳しく解説します。
効果的な回答のポイント
インバスケット試験で高評価を得るためには、以下のポイントを意識して回答することが重要です。
- 優先順位を明確にする
- 論理的な理由を説明する
- 適切な指示や代替案を提示する
1. 優先順位を明確にする
- 業務の緊急度(Urgency)と重要度(Importance)を考慮し、優先順位を決める。
- すぐに対応すべき問題と、後回しにできる問題を判断する。
- 優先順位の理由を明確に説明することで、論理的な思考が評価される。
2. 論理的な理由を説明する
- なぜその判断をしたのかを、明確な根拠とともに説明する。
- 「直感的な判断」ではなく、論理的な思考プロセスを示すことが重要。
- 例えば、「取引先のクレーム対応を最優先するのは、会社の信用に関わるため」など、ビジネスの視点から説明する。
3. 適切な指示や代替案を提示する
- 単に問題を処理するのではなく、関係者への適切な指示や代替案を示す。
- 「誰に」「何を」「どのように」対応するのかを具体的に書く。
- たとえば、部下の育成問題なら、「OJT研修を実施し、指導方法を標準化する」などの改善策を提示する。
回答例を用いた具体的な解説
ここでは、典型的なインバスケット問題に対する回答例を詳しく解説します。
【問題1】取引先のクレーム対応
【問題】
あなたの部署が担当する取引先A社から、「納品された製品に不良品が含まれていた」とのクレームが入りました。
A社は「すぐに交換対応しなければ、今後の取引を見直す」と述べています。
一方で、上司からは「今後の品質管理について社内報告をまとめるように」と指示が出ています。
どのように対応しますか?
【回答例】
まず、A社のクレーム対応を最優先とします。
クレーム対応が遅れると、企業の信用問題につながる可能性があるためです。
直ちにA社の担当者に連絡し、不良品の状況を確認した上で、迅速に交換対応を行います。
同時に、品質管理担当者と協議し、社内での原因調査を進めます。
上司への報告については、品質管理チームに協力を依頼し、調査結果をもとに報告資料を作成します。
【解説】
- 最優先すべきはA社のクレーム対応であることを明確に示している。
- その理由として、「企業の信用問題につながる」という論理的な説明を加えている。
- クレーム対応後の社内処理や上司への報告についても言及し、抜け漏れのない対応を示している。
【問題2】部下のマネジメント(指導・育成)
【問題】
新入社員Bさんが最近、業務のミスが増えています。
先日も顧客対応で誤った説明をしてしまい、クレームにつながる可能性がある事態が発生しました。
あなたはBさんの上司として、どのように対応しますか?
【回答例】
まず、Bさんに対して、今回のミスの具体的な原因をヒアリングします。
その上で、顧客対応のスキルを向上させるために、OJT研修を実施し、先輩社員のロールプレイング指導を行います。
また、Bさんには、業務マニュアルの見直しを促し、同じミスを繰り返さないようフォローします。
今後も定期的に進捗確認を行い、Bさんが自信を持って業務に取り組める環境を整えます。
【解説】
- 「なぜミスが発生したのか」という原因を明確にするプロセスを示している。
- 問題の解決策として「OJT研修」「ロールプレイング」「マニュアルの見直し」など、具体的な施策を提示している。
- 単なる叱責ではなく、部下の成長を促す対応をしている点が評価される。
【問題3】突発的なトラブル対応(システム障害)
【問題】
本日、社内の基幹システムが障害を起こし、一部の業務がストップしています。
IT部門は復旧作業を進めていますが、復旧までに3時間ほどかかる見込みです。
取引先との重要なオンライン会議が1時間後に予定されていますが、通常のシステムが使えない状態です。
あなたは管理職として、どのように対応しますか?
【回答例】
まず、IT部門に詳細な復旧見込みを確認し、影響範囲を把握します。
次に、取引先に速やかに連絡を入れ、システム障害の状況を説明し、オンライン会議の延期または代替手段の提案を行います。
代替手段として、電話会議や別のコミュニケーションツール(Zoom、Teams など)の利用を検討します。
社内向けには、影響を受ける部署に周知を行い、業務の優先順位を見直して最小限の影響に抑えるよう調整します。
【解説】
- 「状況の把握」「関係者への報告」「代替策の検討」の3つのステップが明確になっている。
- トラブル時の対応として、「影響を受ける範囲を把握し、迅速に関係者と調整する」プロセスが示されている。
- 代替策(電話会議や別システムの利用)を提案し、柔軟な対応ができる点が評価される。
その他の回答例を見たい方は以下の記事を参考にどうぞ。

回答を作成する際の注意点
インバスケット試験では、単に問題を解決するだけでなく、管理職やリーダーとして適切な判断ができるかどうかが評価されます。
そのため、回答を作成する際には、以下のポイントを意識することが重要です。
- 感情的にならず、冷静な判断を示すこと
- 事実に基づいた対応策を考えること
- リスク管理を意識し、最適な解決策を提示すること
- 単なる問題処理ではなく、今後の再発防止策も考慮すること
順に見ていきましょう。
1. 感情的にならず、冷静な判断を示すこと
インバスケット試験では、問題が発生した際に「冷静に対処できるかどうか」が重要な評価ポイントになります。
特に、クレーム対応や部下の指導などでは、感情的に反応するのではなく、論理的に状況を判断することが求められます。
【良い回答の例】
取引先のクレームに対して、まず事実関係を確認し、誠意を持って対応します。
取引先が求める対応を把握し、可能な範囲で迅速に問題を解決するよう努めます。
併せて、社内の品質管理部門と連携し、再発防止策を検討します。
【悪い回答の例】
クレームを入れてきた取引先の要求が理不尽なので、こちらの正当性を主張する。
まずは自社の非を認めず、相手の要求が妥当かどうかを議論する。
解説:
→ 感情的に対応すると、事態が悪化する可能性があるため、まずは事実を確認し、冷静に対応策を検討することが大切です。
2. 事実に基づいた対応策を考えること
インバスケット試験では、「思い込み」や「個人的な価値観」ではなく、事実に基づいた判断が求められます。
そのため、問題に対して適切な情報を収集し、客観的なデータや証拠をもとに対応策を考えることが重要です。
【良い回答の例】
部下が業務ミスをした際、まずは具体的なミスの内容を確認し、再発防止策を考えます。
例えば、「業務マニュアルを見直す」「先輩社員とペアを組ませる」といった具体的な対策を実施します。
【悪い回答の例】
「部下のミスは本人の不注意が原因」と決めつけ、厳しく叱責する。
具体的な確認をせず、感覚的に「とりあえず再発防止策を考える」と述べる。
解説:
→ 問題の根本原因を分析し、具体的なデータや事実に基づいた対策を考えることが重要です。
3. リスク管理を意識し、最適な解決策を提示すること
インバスケット試験では、「最適な判断ができるかどうか」だけでなく、「リスクを最小限に抑える判断ができるかどうか」も重要視されます。
問題を解決する際に、短期的な視点だけでなく、長期的な影響や副作用を考慮することが求められます。
【良い回答の例】
システム障害が発生した場合、まず影響範囲を確認し、復旧までの時間を見積もります。
その上で、取引先との会議の延期を交渉するか、代替の通信手段を提案します。
【悪い回答の例】
システムが復旧するまで待つしかないので、特に行動を起こさない。
上司に報告だけして、自分では何もしない。
解説:
→ リスクが発生した際に、「どうすれば最小限の影響で済むか」を考え、迅速に対応することが求められます。
4. 単なる問題処理ではなく、今後の再発防止策も考慮すること
インバスケット試験では、目の前の問題を解決するだけでなく、「同じ問題が繰り返されないようにするための仕組み作り」が重要視されます。
そのため、単に対応策を考えるだけでなく、組織としてどのように改善すればよいかを考えることが評価につながります。
【良い回答の例】
取引先のクレームに対応した後、社内で品質管理の見直しを行い、再発防止策を実施する。
具体的には、「品質管理部門との連携を強化する」「検査体制を改善する」といった施策を講じる。
【悪い回答の例】
その場限りの対応を行い、再発防止策については特に考えない。
「また同じ問題が起きたら、その時に考えればいい」と述べる。
解説:
→ インバスケット試験では、短期的な問題解決だけでなく、長期的な組織の改善視点を持つことが求められます。
- 感情的にならず、冷静かつ論理的に判断する。
- 事実に基づいて対応策を考え、根拠を示す。
- リスク管理を意識し、最小限の影響で済むように対応する。
- 問題を解決するだけでなく、再発防止策も考慮する。
インバスケット試験では、管理職やリーダーとしての適性が評価されるため、上記のポイントを意識しながら解答を作成することが重要です。
回答のコツをより詳しく知りたい方は以下の記事を参考にどうぞ。
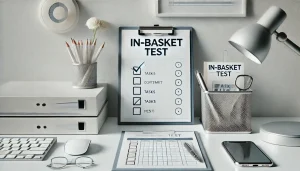
インバスケット試験によくある質問
インバスケット試験を受けるにあたって、受験者が疑問に思うことや悩みを抱えやすいポイントについて解説します。
ここでは、回答時間が足りない場合の対策、求められるスキル、事前に準備しておくべきことについて詳しく説明します。
回答時間が足りない場合の対策
インバスケット試験では、限られた時間内に多くの案件を処理する必要があるため、時間管理が非常に重要です。
試験本番で時間が足りなくなることを防ぐために、以下の対策を実践しましょう。
- すべての案件に一度目を通し、優先順位をつける
- 完璧を求めず、短時間で合理的な判断をする
- 回答をシンプルにし、要点を押さえる
対策1:すべての案件に一度目を通し、優先順位をつける
- 試験が始まったら、まず全体の問題をざっと確認し、どの案件を先に処理すべきかを判断する。
- 緊急度(Urgency)と重要度(Importance)を基準に、優先順位を決定する。
優先順位をつける際の簡単な基準:
| 優先度 | 対応すべき案件の例 |
|---|---|
| 最優先(即対応) | クレーム対応、納期遅れ、重大なトラブル発生 |
| 次に対応 | 部下の指導、社内会議資料作成、業務改善策の検討 |
| 最後に対応 | 長期的な戦略策定、研修計画の立案 |
ポイント:
「とりあえず目についた案件から解く」ではなく、優先順位を決めて戦略的に進めることが大切です。
優先順位の考え方は以下の記事を参考にどうぞ。

対策2:完璧を求めず、短時間で合理的な判断をする
- 限られた時間内で最善の対応を考えることが重要。
- すべての案件を完璧に処理しようとすると、時間が足りなくなるおそれがある。
【対策】
- 1案件あたりに使う時間の目安を決める(例:3分〜5分)
- 情報を整理し、論理的に説明できるレベルで回答する
- 時間をかけすぎそうな案件は、一度保留して後回しにする
ポイント:
100点満点を目指すよりも、80点程度の精度で効率よく回答することが求められます。
3. 回答をシンプルにし、要点を押さえる
- 長文で細かく書くよりも、ポイントを押さえた簡潔な文章で回答する。
- 試験官は「受験者がどのように考えて判断したか」を評価するため、論理的な流れが重要。
【悪い例(冗長な回答)】
まず、部下の業務ミスについて詳細に調査を行い、各関係者にヒアリングを実施した後、問題点を整理し、原因を分析し、解決策を検討する。さらに、研修プログラムを組み直し、改善策の実行計画を策定して…
【良い例(簡潔な回答)】
部下のミスの原因を確認し、OJT研修を実施。業務マニュアルを更新し、ミスの再発を防ぐ。
ポイント:
簡潔かつ論理的に説明することで、時間を節約し、より多くの問題に対応できるようになります。
どのようなスキルが必要か
インバスケット試験では、以下のスキルが重要視されます。
1. 論理的思考力(ロジカルシンキング)
- 複数の情報を整理し、筋道を立てて考える力。
- 「なぜこの判断をしたのか」を説明できるようにする。
【対策】
- 「なぜこの対応が必要なのか?」と自問しながら回答を作成する習慣をつける。
- 日常業務でも、論理的に考えるクセをつける。
2. 優先順位設定能力(タイムマネジメント)
- 複数の案件の中から、どれを最優先で対応すべきかを判断する能力。
- 緊急度と重要度を基準に、業務の取捨選択を行うことが求められる。
【対策】
- 「この業務は今すぐ必要か?」と考え、業務の優先順位を決める練習をする。
- 普段の仕事でも、優先順位を意識しながらスケジュールを組む。
3. コミュニケーション能力(報連相)
- 部下、上司、取引先など、さまざまな関係者と適切にコミュニケーションを取る力。
- 報告・連絡・相談を的確に行い、組織の中で円滑に業務を進めることが求められる。
【対策】
- 短時間で要点を伝える訓練をする(結論→理由→具体例の順で話す)。
- 相手の立場を考え、必要な情報を的確に伝える意識を持つ。
上記以外の求められるスキルの詳細は以下をご覧ください。

事前に準備しておくべきこと
1. 過去問や模擬試験を解く
- 実際の試験形式に慣れることが重要。
- 過去問を使って、時間配分の感覚を掴む。
過去問を解きたい方は以下の記事を参考にどうぞ。


2. 業務の優先順位を考える練習をする
- 日々の仕事でも、「今やるべき業務は何か?」を考える習慣をつける。
- 重要度と緊急度を意識しながら、業務を整理する。
3. 短時間で意思決定する訓練をする
- 普段の仕事でも「素早く判断する」ことを意識する。
- 限られた時間の中でベストな選択をする練習を積む。
回答時間が足りない場合の対策:
- すべての案件を確認し、優先順位を決める
- 完璧を求めず、短時間で合理的な判断をする
- 回答をシンプルにし、要点を押さえる
求められるスキル:
- 論理的思考力(筋道を立てて考える力)
- 優先順位設定能力(業務の取捨選択をする力)
- コミュニケーション能力(適切な報連相を行う力)
事前に準備しておくべきこと:
- 過去問や模擬試験を解く
- 業務の優先順位を考える練習をする
- 短時間で意思決定する訓練をする
まとめ|インバスケットの特徴と試験対策
- インバスケット試験とは?
- 限られた時間内に複数の業務案件を処理する試験
- 管理職やリーダーの判断力・問題解決能力を評価する
- インバスケットの特徴
- 実務に近い試験形式で、知識よりも実践的なスキルが求められる
- 正解が1つではなく、論理的な判断プロセスが評価される
- インバスケット試験の問題形式と対策
- 優先順位の判断が重要(緊急度×重要度で整理)
- クレーム対応、部下の指導、トラブル対応など、多様な問題が出題される
- 時間管理を意識し、シンプルかつ論理的な回答を心がける
- 試験で求められるスキル
- 論理的思考力(なぜその判断をしたのか説明できるか)
- 優先順位設定能力(最も重要な業務を見極める力)
- コミュニケーション能力(部下や上司と円滑に業務を進める力)
- 事前に準備しておくべきこと
- 過去問や模擬試験を解き、試験形式に慣れる
- 普段の業務でも、優先順位を意識しながら仕事をする
- 短時間で意思決定する訓練を行う
インバスケット試験の特徴をある程度理解できたら、実際の問題を解いてみるとよいでしょう。
実際の問題は以下の記事をご覧ください。


